BLOGブログ
【冬から注意】子供の水疱瘡(みずぼうそう)|症状や潜伏期間、予防接種について

こんにちは。
突然全身にブツブツが…。
水ぼうそうはご存じの方も多いかと思います。
水ぼうそうは正式には水痘(すいとう)と呼ばれる病気です。
今回は、水ぼうそうの症状や、治療方法、ワクチンはあるかなどについて詳しく解説していきます。
Contents
なぜ子供は水疱瘡(みずぼうそう)に罹りやすいのか

原因
水痘帯状疱疹ウイルス(VZV:ヒトヘルペスウイルス3型)によって引き起こされます。
潜伏期間
感染から2週間程度(10〜21日)経ったのち発症します。
免疫不全のある人は通常の潜伏期間より長くなることもあります。
感染経路
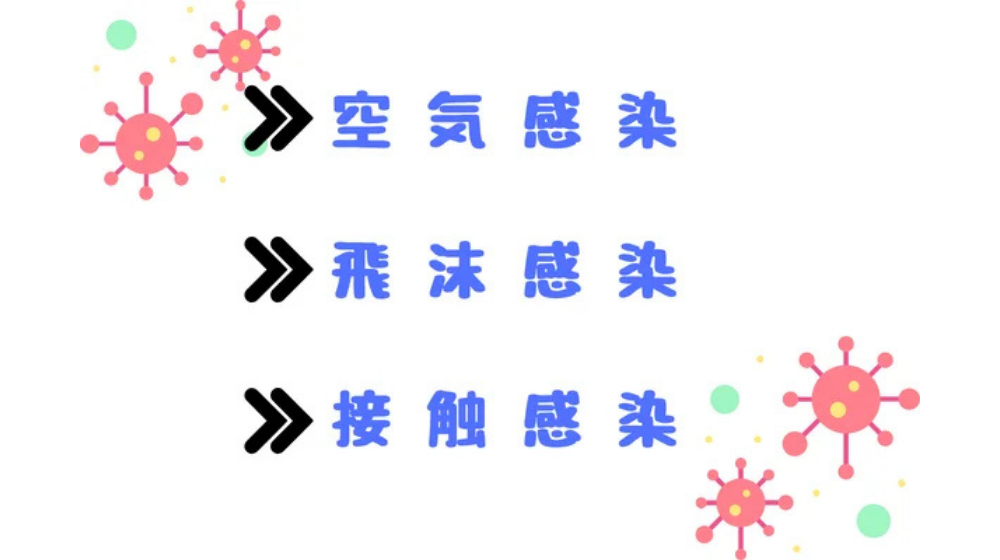
水ぼうそうは極めて感染力が強く、麻疹(はしか)よりは弱いものの、おたふくかぜや風疹よりは強いとされています。
空気感染・飛沫感染・接触感染によって広がり、具体的には以下のような経路を介して感染します。
- ウイルスを含んだ飛沫やエアロゾル(飛沫より小さく、空気中に長時間留まりやすい)を吸い込む
- ウイルスが含まれる皮膚病変(水ぼうそう患者さんの皮膚のブツブツ)を直接触った手などを介して鼻や口から体内に入る
通常は鼻や口から入ったあと気道の粘膜に付着して感染、付着した粘膜とリンパ節でウイルスの数を増やします。
感染後4〜6日すると一次ウイルス血症という血液への感染を起こします。
ウイルスは肝臓や脾臓などの臓器に広がっていきます。
更にそこで増えたのち、ニ次ウイルス血症を起こして皮膚に発疹が現れます。
水ぼうそうは発疹出現の1〜2日前から発疹が出現してから4〜5日にかけて最も感染力が強いです。
発疹が出現する1〜2日前から全ての発疹が痂皮化(かさぶた化)するまで感染力を有します。
流行時期

12〜7月にかけて多くみられ、8〜11月は減少傾向にあります。
なぜ子どもに多い?
水ぼうそうは主に小児の病気で、9歳以下での発症が90%以上を占めるとされています。
水痘帯状疱疹ウイルスの初感染で水ぼうそうを引き起こします。
幼少期の感染はすなわち初感染と考えられるため、水ぼうそうは子どもに多い病気なのです。
ちなみに、水痘帯状疱疹ウイルスは治癒後も神経節に潜伏感染しています。
そのため、加齢や免疫低下に伴って再活性化し、帯状疱疹を起こします。
大人(特に高齢者)によく帯状疱疹がみられるのはこのためです。
なお、我が国における水痘帯状疱疹ウイルスに対する抗体保有率は小児では低く、大人になるにつれて高く、55歳以上では100%となります(ただしワクチンによる抗体獲得者も含む)。
つまり日本人のほとんどがかかるウイルスといえます。
関連記事:りんご病(伝染性紅斑)になったら病院へ行くべき?症状を解説|大人にもうつる?
水疱瘡(みずぼうそう)の症状について

初期症状
軽い頭痛や発熱、全身のだるさなどといった症状が、発疹が出現する2〜3日前に現れる場合があります。
この症状は10歳以上の子どもでみられることが多く、成人ではより重い症状となります。
発疹
最初の発疹は斑点状で、紅斑(赤み)を伴うこともあります。
数時間以内に発疹は丘疹(盛り上がったような発疹)となり、その後はかゆみを伴った小さな水疱(水ぶくれ)が赤みの上に現れます。
最後は痂皮化(かさぶた化)し、治癒します。
数日にわたり新しい発疹が次々と出現するので、急性期には紅斑・丘疹・水疱・痂皮のそれぞれの段階の発疹が混在します。
新たな発疹は通常5日目までに現れなくなり、大部分は6日目までに痂皮化します。
発症後20日未満で大半の痂皮は消失します。
発疹は頭部〜顔面、体幹部(胸・腹・背中)から始まり、次々に発疹が現れて全身へと広がっていきます。
特に体幹部は発疹が多くみられ、発疹が全身に広がらない場合も体幹部には必ず出ると言われています。
発疹が口の中や鼻・喉の粘膜、眼の結膜、直腸や腟などの粘膜に発生することもあります。
口の中にできた水疱は破れやすく、食べたり飲んだりする時に痛みを伴います。
頭皮に発疹が出た場合、後頭部や後頚部(首の後ろ)のリンパ節に腫れや痛みが生じることもあります。
なお、近年の統計によると、我が国において水ぼうそうは年間100万人程度が発症。
4,000人程度が入院、20人程度が死亡していると推定されている疾患です。
合併症
水ぼうそうは一般的に軽症で、免疫が正常な子どもでは重症化することはまれです。
15歳以上の成人や1歳以下の乳児、免疫の低下した人では重症化し、合併症を伴うことがあります。
通常、咳や鼻水などの呼吸器症状や、腹痛や下痢、嘔吐などの消化器症状を伴うことはないとされています。
しかし、時に肺炎(水痘肺炎)などを引き起こすこともあります。
水ぼうそうに合併する肺炎は通常ウイルス性ですが、細菌性の場合もあります。
また、それらに伴って脱水症を起こすこともあります。
心筋炎や肝炎、出血性疾患などを合併することもあります。
その他、合併症としては以下のものが挙げられます。
*皮膚の二次性細菌感染
水ぼうそうの発疹に細菌(典型的にはレンサ球菌またはブドウ球菌)が感染し、一般的な水ぼうそうとは違う皮膚病変が出現したり、症状が悪化したりします。
かゆみで発疹をかきむしってしまうと、そこから細菌が入ってしまう場合があります。
細菌感染を起こした場合は抗生物質などで治療します。
原因菌を抑えられれば、水ぼうそうの回復に伴って症状も次第に改善されていきます。
蜂窩織炎(ほうかしきえん)(*1)や、ごくまれに壊死性筋膜炎(えしせいきんまくえん)(*2)やレンサ球菌による毒素性ショックを引き起こす場合があり、生命に関わるため注意が必要です。
*1蜂窩織炎(ほうかしきえん)=皮膚とそのすぐ下の組織に生じる、広がりやすい細菌感染症
*2壊死性筋膜炎(えしせいきんまくえん)=皮膚の深いところ、つまり筋肉を覆う筋膜の上に起こる細菌感染症
*無菌性髄膜炎・脳炎
水痘帯状疱疹ウイルスが原因によって引き起こされる「水痘帯状疱疹ウイルス性髄膜炎」という病気があります。
水痘帯状疱疹ウイルスによる髄膜炎と診断された場合は、速やかにアシクロビルなどの抗ウイルス薬の投与が行われます。
炎症が脳にまで及ぶと脳炎となり、生命に関わります。
成人の水ぼうそう重症例にみられ、1000例に1〜2例の頻度で発生するとされています。
*小脳炎
水ぼうそうには様々な神経系合併症がみられますが、最もよくみられるのがこの小脳炎です。
水ぼうそうなどのウイルス感染がきっかけとなって小脳に炎症が起き、小脳の機能が侵されます。
水ぼうそうに罹患した小児の約4000人に1人の割合でみられます。
小脳には歩行に関する機能や手足の協調運動(例:食事をする、スキップをする、服を着替える)を取りまとめる機能があります。
小脳炎になると急にふらついて上手く歩けなくなったり、協調運動が障害されたりします(急性小脳失調と呼ばれます)。
数週間で自然に治癒するため、診断されても特に治療はせず経過観察のみが行われます。
症状が強い・長引く場合は、副腎皮質ステロイドやγ-グロブリンの投与などといった治療を行うこともあります。
*ライ症候群
はっきりとした原因は不明ですが、一般的にはインフルエンザや水ぼうそうなどのウイルス感染症にかかった際に、治療でアスピリンを服用した子ども(主に18歳未満)にみられます。
インフルエンザや水ぼうそうなどの症状に続いて、激しい吐き気や嘔吐、錯乱、反応が鈍くなるなどといった症状がみられ、時には昏睡状態に陥ることもあります。
脳へのダメージの程度によって予後が変わります。
このように、アスピリンはライ症候群のリスクを高めるため、一部の特定の病気(若年性特発性関節炎や川崎病)にかかっている場合を除いて、子どもへの投与は推奨されていません。
今ではこういった過去の事例からアスピリンの使用が減ったため、ライ症候群を発症する人はほとんどみられません。
アスピリンを処方されていないか、保護者の方はお薬の内容に注意しておくことも大切です。
かかった後は?
水ぼうそうにかかった後は終生免疫を得て、その後感染しても症状が出ることはありません。
水疱瘡(みずぼうそう)と虫刺されやあせもとの違い

虫刺され

水ぼうそうの初期は虫刺されとよく似ており、区別が難しいことがあります。
水ぼうそうの場合は全身に発疹がみられ、頭皮や口の中にも発疹があることが多いです。
頭皮や口の中にも発疹が出ていれば水ぼうそうの可能性が高くなります。
しっかりと経過を見ることが重要です。
関連記事:ダニ刺され・刺された跡で悩んでいる人必見!あせもとの違いは?|症状や治療についても
あせも

汗を出す管が何らかの原因によって詰まり、炎症が起きた状態のことをいいます。
汗をかきやすい夏によくみられます。
以下など、汗をかきやすく蒸れやすい部位に赤みを伴った小さな発疹が現れます。
- 頭(髪の生え際)
- 首のまわり
- 脇の下
- 肘・膝関節の裏
- ベルトや下着で締め付けのある部分
水ぼうそうと同じく、水ぶくれが出ることもまれではありません。
虫刺されの場合と同様、全身に発疹が出現し、頭皮や口の中にも発疹がみられる場合は水ぼうそうを疑いましょう。
関連記事:子どもが汗疹(あせも)になったときはどうすればいい?治し方や湿疹との違い・対策法について
軽い水疱瘡(みずぼうそう)は気づきにくい?注意点について

水ぼうそうは上記の通り、他の疾患と間違われる場合があります。
また、症状が軽い場合、水ぼうそうと気付かずに過ごす可能性もあります。
子どもの水ぼうそうは通常、重症化せずに治癒します。
しかし、前述の通り15歳以上の成人や1歳以下の乳児、免疫の低下した人では重症化することがあります。
時に生命に関わることもあるため、少しでもあやしいと思ったら受診することが大切です。
受診の目安は?

赤い斑点や水ぶくれ、発熱(無い場合もあります)などがみられたら受診しましょう。
ただし水ぼうそうは感染力が強く、周りの人にうつす可能性が高いです。
水ぼうそうが疑われる場合は、事前に病院に伝えてから受診するのが望ましいと考えます。
登校や登園の目安は?

学校保健安全法において、水ぼうそうは第二種の感染症に指定されています。
そのため、「全ての発疹が痂皮化するまで」は出席停止となります。
個人差がありますが、およそ1週間程度は出席停止になると考えてください。
また、以下の場合も出席停止期間となります。
①患者のある家に居住する者又はかかっている疑いがある者については、予防処置の施行その他の事情により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで
②発生した地域から通学する者については、その発生状況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間
③流行地を旅行した者については、その状況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間
水疱瘡(みずぼうそう)は大人にもうつるのか

水ぼうそうは前述の通り子どもの病気と思われがちですが、大人でも感染します。
大人が水ぼうそうにかかると重症化し、水痘肺炎などの重い合併症を起こす頻度が高くなります。
妊婦さんの場合
| 妊娠20週頃までに水ぼうそうになった場合 | 1〜2%の割合で先天性水痘症候群を発症します。胎児や新生児に重い障害が出現し、死産に至る症例もまれに報告されています。 |
| 分娩前5日~産後2日間に妊産婦が水ぼうそうになった場合 | 新生児は胎盤を通してウイルスに感染します。しかし、母親からの移行抗体が間に合わず重篤化しやすくなります。 |
関連記事:風疹(風しん)はどんな症状が出る?妊娠時に気をつけるべき理由と感染経路について
水疱瘡の予防接種について
水ぼうそうに対する予防接種は、我が国では平成26年10月1日から定期接種となっています。
水痘ワクチンの定期接種は、1歳の誕生日の前日から3歳の誕生日の前日までの子どもが対象です。
また、予防接種は2回行うこととなっています。
接種期間の目安は以下の通りです。
| 1回目の接種 | 原則として生後12ヶ月〜生後15ヶ月までの間に行います。 |
| 2回目の接種 | 1回目の接種から3ヶ月以上経過してから行いますが、標準的には1回目の接種後6ヶ月〜12ヶ月を経過してから行うこととなっています。 |
なお、すでに水ぼうそうにかかったことのある子どもは、水ぼうそうに対する免疫を獲得していると考えられます。
そのため、基本的には定期接種の対象外です。
一定の頻度でみられる接種後の副反応については下記のとおりです。
| 過敏症 | 接種直後から翌日に発疹、じんましん、紅斑、かゆみ、発熱などが現れることがあります。 |
| 全身症状 | 発熱や発疹がみられることがあります。一過性のものであり、通常は数日中に消失するとされています。 |
| 局所症状 | 発赤、腫脹、硬結などが現れることがあります。 |
まれに報告される重い副反応としては、アナフィラキシー様症状、急性血小板減少性紫斑病などがあります。
ブレイクスルー水痘
まれに、予防接種を受けた小児が水ぼうそうを発症することがあります(ブレイクスルー水痘と呼ばれます)。
この場合、発疹は通常より軽度であり、発熱の頻度はより低く罹患期間はより短いとされています。
水疱瘡(みずぼうそう)になったときの治療について

対症療法が基本となります。
抗ウイルス薬(アシクロビル・バラシクロビル・ファムシクロビル)がありますが、通常の場合投与は不要とされています。
重症化リスクのある人については、発疹出現後24時間以内の投与が推奨されます。
細菌の二次感染を予防するために、定期的に入浴して服や手を清潔に保ち、爪も切っておきましょう。
消毒薬は、原則として使用すべきではありません。
細菌の二次感染がある場合は抗生物質を使います。
全身状態に問題がなければ外来受診および自宅での経過観察が可能な病気です。
ただし、空気感染もする感染力の強い疾患です。
痂皮化するまでは他の人との接触を避ける必要があります。
一方で、重い合併症がみられる場合や免疫不全のある方は、医療機関に入院のうえ治療が必要となります。
まとめ
今回は水ぼうそうの症状や、治療方法、ワクチンはあるかなどについて解説しました。
感染力の強い水ぼうそうは、周りの人にもうつすことがあるため注意が必要です。
また、妊婦さんが感染するとお腹の中の子どもに影響をおよぼす場合もあります。
水ぼうそうはワクチンで予防できます。
予防接種はお忘れなく!
参考文献