BLOGブログ
脳梗塞の前兆チェック|予防するための3つのポイントを解説
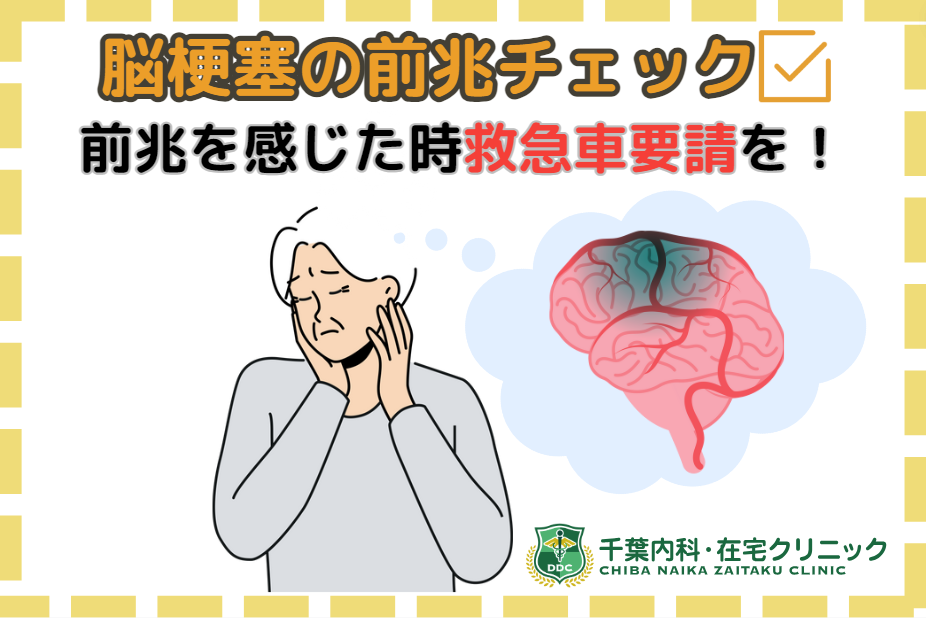
脳梗塞は、日本人の死因の上位を占める重大な病気です。
しかし、早期発見と適切な治療で後遺症を最小限に抑えることができます。
今回は、脳梗塞の症状や前兆、そして緊急時の対応方法、さらに日常生活での予防法まで、命を守るために知っておきたい知識を、わかりやすくお伝えします。
「もしも」のときに慌てないよう、ご家族みなさんでぜひ確認してください。
Contents
脳梗塞とは?

脳梗塞は、脳の血管が詰まって血液の流れが悪くなり、脳の細胞が酸素や栄養を受け取れなくなる病気です。
血管が詰まってから4時間半以内に治療を始めることが大切です。
この「ゴールデンタイム」と呼ばれる時間内に治療を受けられるかどうかが、回復の大きな分かれ目となります。
脳梗塞は、次のように3つのタイプに大きく分かれます。
アテローム血栓性脳梗塞
動脈硬化によって血管が狭くなり、その部分で血栓(血の塊)ができて血管が詰まるタイプです。
心原性脳塞栓症
心臓でできた血栓が血流に乗って脳の血管を詰まらせるタイプです。
心房細動という不整脈が原因のことが多いです。
ラクナ梗塞
脳の奥の細い血管が詰まるタイプで、比較的小さな範囲に影響を与えますが、繰り返すことで重篤な症状が出ることもあります。
脳梗塞の主な症状

片側の手足の麻痺や脱力
体の片側(右半身または左半身)が突然動かなくなったり、力が入らなくなります。
足や手が動かしにくくなるだけでなく、顔の片側が垂れ下がることもあります。
言語障害
言葉が突然うまく話せなくなったり、相手の言っていることが理解できなくなる「失語症」が見られることがあります。
また、呂律が回らなくなることもあります。
視力の低下や視野の欠損
視力が急に低下したり、片側の視野が見えなくなることがあります。
これにより、物が二重に見えることや、物の一部が見えなくなることがあります。
めまいやふらつき
平衡感覚を失い、突然ふらついたり、めまいが生じます。
また、歩行が困難になることもあります。
意識障害や混乱
突然、ぼんやりしたり、意識がもうろうとすることがあります。
また、記憶が一時的に混乱することもあります。
激しい頭痛
脳梗塞では頭痛がそれほど顕著でない場合もありますが、脳出血と合併するケースでは、突然の激しい頭痛を伴うことがあります。
脳梗塞の前兆チェックシート
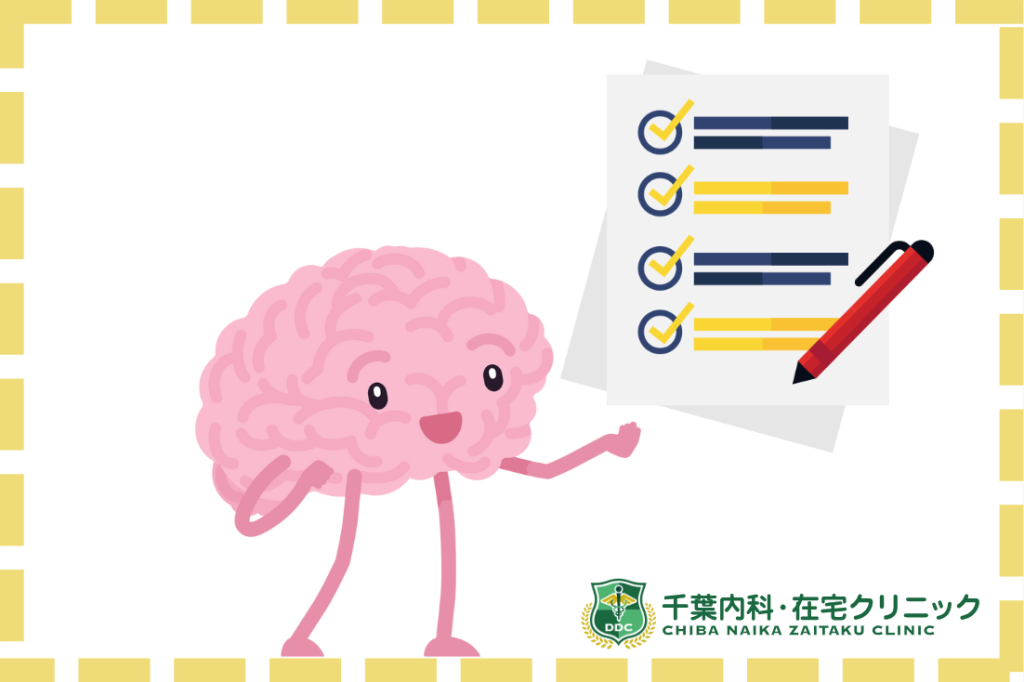
脳梗塞の前兆を早期に発見できるよう、以下の5つのカテゴリーに分けたチェックシートを作成しました。
ひとつでもチェックがある場合は、脳梗塞の前兆の可能性があります。
すぐに医師の診察を受けることを強くお勧めします。
脳梗塞は早期発見・早期治療が重要で、早ければ早いほど後遺症を防ぐことが可能です。
運動障害
言語障害
感覚障害
視覚障害
平衡感覚障害
関連記事:知ってほしい脳卒中の危険な前兆・症状や脳梗塞との違いは?
脳梗塞の前兆を感じた時は救急車要請?

脳梗塞が疑われる症状が出たら、すぐに119番通報をしましょう。
「様子を見よう」という判断が、取り返しのつかない事態を招くことがあります。
たとえ症状が一時的に良くなっても、これは「一過性脳虚血発作」と呼ばれる危険な状態で、本格的な脳梗塞の前触れである可能性が高いです。
救急車を呼ぶことで、適切な病院への素早い搬送と、専門的な初期対応を受けることができます。
救急車の要請は慎重に行うべきですが、脳梗塞の可能性がある場合、救急車を利用することは医療資源の適正な利用に該当します。
脳梗塞は迅速な治療で後遺症や死亡率を大幅に減らせるため、早期治療が後の医療負担(長期入院やリハビリ、後遺症のケア)を減少させます。
- 自力での病院搬送は危険
症状が進行する可能性があり、病院に到着するまでに時間がかかると、治療効果が減少します。 - 救急車が適切に使われるべき理由
救急隊は、発症時間の確認や初期の対応を行い、専門施設に直行することで治療開始までの時間を短縮できます。
脳梗塞を予防するための3つのポイント

脳梗塞を予防するためには、日常生活でできる対策が非常に重要です。
以下に、早期発見、食生活、適度な運動の3つに分けて説明します。
早期発見
早期発見は脳梗塞の予防において非常に重要です。
脳梗塞の前兆やリスク要因に気をつけることで、発症を防いだり、重篤な後遺症を避けることが可能です。
- 定期的な健康診断
高血圧、糖尿病、高コレステロールなどのリスク要因を早期に発見し、適切な治療を受けることが重要です。 - 脳ドック
専門的な検査も脳梗塞のリスクを把握するために有効です。 - 前兆症状を知る
突然の片側の麻痺、言語障害、視覚障害、めまいなどの症状が現れたらすぐに医療機関に連絡することが必要です。
食生活
食生活の改善は脳梗塞の予防に直結します。
血管の健康を保ち、血液をサラサラに保つ食事を心がけることが重要です。
- 塩分の摂取を控える
高血圧は脳梗塞の主な原因です。
塩分の多い食事は高血圧を引き起こすため、1日7g以下を目指しましょう。
特に、加工食品や外食は塩分が多いので注意が必要です。 - バランスの取れた食事
野菜、果物、全粒穀物、魚を中心とした食事を心がけ、コレステロールや飽和脂肪酸の摂取を控えます。
これにより、動脈硬化を防ぎ、血管の健康を保つことができます。 - 魚やオリーブオイルを使った脂肪の良質な摂取
EPAやDHAが豊富な魚(サバ、イワシ、サーモンなど)は、血液をサラサラにし、脳梗塞のリスクを減少させます。
適度な運動
適度な運動は、脳梗塞を予防するうえで非常に効果的です。
運動は血流を改善し、心血管系の健康を保つだけでなく、高血圧や肥満などのリスクを軽減します。
- 有酸素運動を習慣に
ウォーキングやジョギング、水泳、自転車などの有酸素運動は、血流を促進し、心臓や血管にかかる負担を軽減します。
週に150分以上の中等度の運動を目標にしましょう。 - 適度な筋力トレーニング
筋力を維持することで、基礎代謝が向上し、肥満を予防します。
肥満は脳梗塞のリスクを高めるため、体重管理は重要です。 - 日常生活に運動を取り入れる
エレベーターを使わずに階段を利用したり、日常的に歩く習慣をつけることで、運動の機会を増やすことができます。
関連記事:生活習慣病って何種類あるの?予防対策や検診についても紹介
千葉内科・在宅クリニックでできること
当院では脳梗塞の危険因子となる高血圧症・2型糖尿病・脂質異常症、即日で検査結果をお伝えできる最新の血液検査機器のドライケムを導入しています。
他にも、超音波機器・心電図機器等を導入しており、検査を受けたその日に検査結果をお伝えさせていただけます。(一部の特殊検査を除く)
検査結果で異常を認めた際には、追加で精密検査や診察を受けていただく為に、専門機関や医療機関へ情報提供を行い、紹介受診をしていただくことが可能です。
お困りの際は、是非お気軽にお問い合わせください。
まとめ
脳梗塞は恐ろしい病気ですが、予防と早期発見・早期治療が何より大切です。
本記事で紹介した前兆チェックシートを定期的に確認し、気になる症状があればためらわず救急車を呼びましょう。
また、日常生活での予防も重要です。
適切な食事と運動を心がけ、定期的な健康診断で自身の状態をチェックすることで、脳梗塞のリスクを下げることができます。
あなたと大切な人の命を守るため、この知識を家族で共有し、いざというときに適切な行動がとれるよう備えておきましょう。
参考文献
- 日本脳卒中協会(https://www.jsa-web.jp/)
- 日本脳神経学会(https://www.jns.or.jp/)
- World Stroke Organization (https://www.world-stroke.org/)

千葉内科在宅・美容皮膚科クリニック 院長 辺土名 盛之(へんとな もりゆき)
経歴
- 三重大学医学部医学科 卒業
- 四日市羽津医療センター
- 西春内科・在宅クリニック
- 千葉内科在宅・美容皮膚科クリニック院長